12月1日の夜、福島県二本松市にある男女共生センターで5回目の福島百年未来塾が開かれた。今回の講師は諏訪中央病院名誉院長の鎌田實さん。作家でもある鎌田さんが作詞し、加藤登紀子さんが歌う「ふくしま・うた語り」のCDが流れる中、講演は始まった。
1991年以降21年間、チャルノブイリ原発事故による放射能汚染を受けたベラルーシ共和国に98回医師団を派遣してきた。放射能汚染の最も高いベトカ地区には現在1万9000人もの人びとが生活している。一旦、土地を離れても元の生活に戻りたい年寄たちが帰ってくる例が多い。野菜を育て、森の野草やキノコを採取し、猪などの動物を狩る暮らしが当たり前だった地区の住民たちに対し、しっかりした食品の放射能検査を行って「見える化」し、徹底した食の管理を実施することで内部被曝を減少させる取り組みが地元の医師や病院によって行われているという。
3・11以降、福島に住みつづけている人にとっても、県外に移った人にとっても不安な生活が続いているが、不安を軽減できる事実も出てきている。今年4月以降、福島県内のホールボディカウンターによる検査で、内部被曝している子どもは1人も出ていないこと。また、甲状腺癌の早期発見のために実施されているエコー検査で、嚢胞やしこりがあるとしてA2判定を受けた福島の子どもの割合は昨年35%だったが、福島県以外の子どもたちの同様の検査でも30%代の結果が出ていて、あまり隔たりはないこと、など(A2判定とはその後2年半は経過観察が必要というもので、その後癌になるケースはほとんどないという)。
山形市に子どもと避難しているお母さんたちは、避難してきた自分たちは大丈夫だが、単身で福島に残っている夫が精神的に参っていて、やはり戻って家族一緒に暮らしたいが、放射線の影響は大丈夫なのか不安に感じている。チェルノブイリとの関わりの経験からわかっているのは、こうした事態のなかで大切なことは、①しっかりした検診を実施し、②放射能を「見える化」し、③保養をすること、である。新陳代謝の活発な子どもは、短期間の保養でも身体状況は急速に改善する。チャルノブイリでは、放射能被害を受けた子どものうち12万人が海外支援により国外の保養先へ受け入れられた。鎌田さんの交流しているベラルーシの医師によれば、現在、青年に成長し、自由な外国を見た彼らは、社会貢献しようという意志のある人が多く、ベラルーシの宝になっているという。「絶望の中でも未来に向かうプラスのものを作り出していくことが本当に大切だと感じている」という鎌田さんの結びの言葉が心に残っている。
報告:疋田美津子(ひきた・みつこ/APLA共同代表)


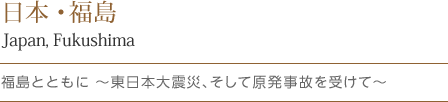

















![旅するシェフと作った!ぽこぽこバナナカレー (4パック入り)【送料込み】[2020円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/bnn_pococurry1.jpg)
![コーヒー飲みくらべ 南米セット(ナチュラレッサ&ブレンド)【送料込み】[2450円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/nomikurabe_ble_org.jpg)
![【セール】チョコラ デ パプア タブレット オーレ&ビター食べくらべセット[1640円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/cco_01_tablet100set.png)
![【10%オフ】クラフトチョコレート カカオキタパプア ミルクココナッツ[1093円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/craft_coco.png)
![【10%オフ】みんなでつくるコーヒー豆チョコレート[642円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/coffeebeans_choco1.png)








